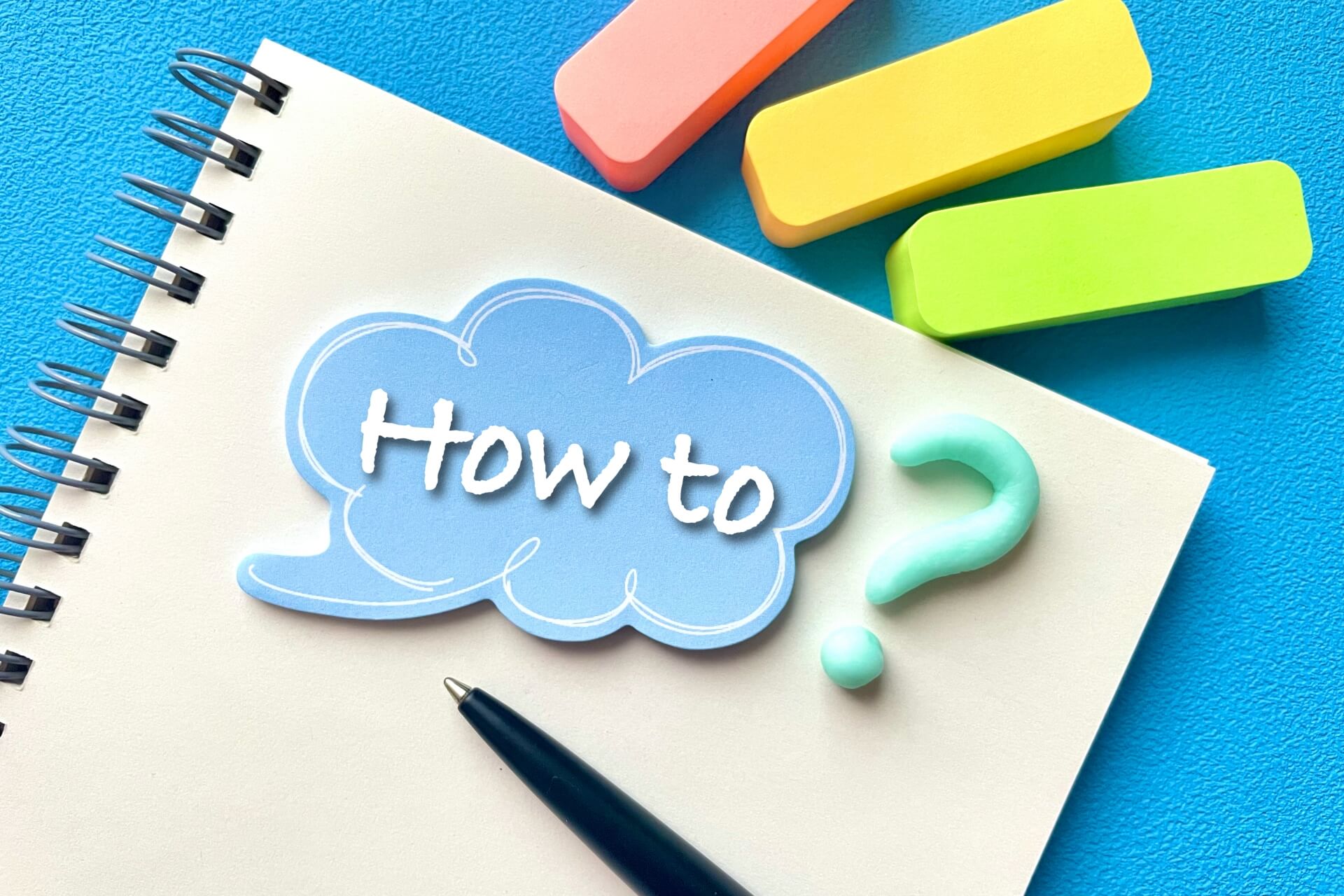So-netの有償オプションサービス【So-net 安心サポート】のリモートサポートページをお探しでしょうか。
このページ「rc50.jp」は、過去に遠隔サポート・リモートサポート窓口として使用されていましたが、今は別の運営者が管理しています。
ここでは【So-net 安心サポート】の公式サイトと使い方、解約方法をご案内します。
So-net 安心サポートのリモートサポートを使いたい方

画像出典:So-net 安心サポート|So-net公式サイト
So-net 安心サポートのリモートサポートを使いたい方は、下記の公式サイトをご確認ください。
\ サービスの使い方はクリック /
So-net 安心サポートを解約したい方
So-net 安心サポートを解約したい方は、下記の公式サイトをご確認ください。
\ So-net 安心サポートの解約はクリック /
So-net 安心サポート(電話+リモートサポート)とは

So-net 安心サポートは、専門スタッフが電話でユーザーと話しながら遠隔でパソコンを確認し、疑問や不安、トラブルをサポートする有料サービスです。
こんなお悩み、So-net 安心サポートで相談できます!
So-net 安心サポートでは一般的なPCトラブルはもちろん、So-netのサービスならではの以下のようなお悩みも解決に導きます。
- 「So-net 安心設定サポート」のアプリで何ができるのか分からない
- So‑netのメールアドレスをスマホやPCのメールアプリに設定したい
- 「So‑netのIPv6接続オプション(v6プラス)」に申し込んだけど設定方法が分からない
- So-net メールアドレスを新しいスマホで使うための設定手順が知りたい
- So-net提供のルーターの「ランプの意味」が分からない
So-net 安心サポート(電話+リモートサポート)の利用方法

So-net 安心サポート(電話+リモートサポート)の利用の流れは下記のとおりです。
はじめにサポート専用電話番号へご連絡ください。
※専用電話番号はマイページまたは、送付された案内冊子に記載されています。
ユーザーが直面している「インターネットに繋がらない」「設定がわからない」などのお困りごとを、専門のオペレーターが丁寧にヒアリングします。
会員専用電話受付時間:9:00~21:00
(※1月1日、2日および指定のメンテナンス日を除く)

オペレーターはユーザーの状況を伺い、口頭での案内で解決できないかどうか試みます。
電話だけでは解決が難しいとオペレーターが判断した場合「リモートで画面を拝見しながらご案内しますか」と提案があります。
ユーザーの許可なく接続することはありませんので、ご安心ください。

オペレーターの案内に従い、サポートを受けたいパソコンで公式サイトの「リモートサポート開始」ボタンをクリックします。
次に、オペレーターから口頭で伝えられる接続コード(数字)を入力して、リモートサポートの開始です。
サポートを受けたい端末で公式サイトのボタンをタップし、専用のサポートアプリをインストールしましょう。
※Apple IDやGoogleアカウントが必要になる場合あり
オペレーターがユーザーの画面を見ながらマウスポインタ等で操作箇所を示したり、代理で設定を行ったりして問題解決を支援します。
So-net 安心サポートに関するよくある質問(FAQ)

BIGLOBEお助けサポート+(プラス)に関する、よくある質問をまとめました。
インターネットやパソコン関連情報 / 役立つコンテンツ

ここでは、日頃のインターネットやパソコン利用に役立つ情報を紹介します。
【初めてでも安心】年賀状ソフトの使い方がわからない|まず確認したい基本の3ステップ

年末が近づくと、準備を始める方も多いのが年賀状作りですね。
しかし「いざ年賀状ソフトを開いてみたけど、何から手をつければいいか分からない…」そんなお悩みはありませんか?
専門のサポートに連絡する前に、まずは基本となる3つのステップを確認してみましょう。

まず、年賀状のメインとなるデザイン面(裏面・文面)を作成します。
- ソフトを起動し「新規作成」を選ぶ
ソフトを立ち上げ「新規作成」「裏面(文面)から作成」などのボタンをクリックします。 - デザインのテンプレートを選ぶ
「デザインナビ」や「デザインを選ぶ」などの項目から、ソフトに収録されている豊富なテンプレート(完成済みのデザイン)を表示させます。
「家族向け」「ビジネス向け」「写真を入れる」など、カテゴリ別に探せる場合がほとんどです。
お気に入りのデザインを選びましょう。 - 写真や文章を編集する(必要な場合)
写真を入れるデザインの場合は「写真を追加」ボタンから、使いたい写真データを選択します。
「賀詞(謹賀新年など)」や「添え書き(昨年はお世話になりました、など)」の文章も、クリックすれば自由に変更・追加できます。
最初から完璧を目指さず、まずは好きなデザインを選んでサンプル文章を少し変えてみるだけでも大丈夫です。
次に、送り先の住所や名前を入力する宛名面(表面)を作成します。
- 住所録を新規作成する
ソフトのメニューから「宛名面を作成」「住所録を開く」などを選択し「新しい住所録を作る」をクリックします。 - 1件ずつ情報を入力する
「氏名」「敬称(様など)」「郵便番号」「住所」となどの項目が表示されるので、お手元の住所リストを見ながら1件ずつ入力していきます。
入力が終わったら「登録」「保存」ボタンを押して、次の人の情報を入力します。 - 差出人情報を登録する
忘れずに、ご自身の住所・氏名である「差出人」の情報も登録しておきましょう。
「差出人設定」などのメニューから入力できます。
住所録は一度作ってしまえば、来年以降もずっと使えます。
最初は少し大変ですが、頑張って入力してしまいましょう。
Excelなどで住所録データをお持ちの場合は「外部データ取り込み」機能で一括登録できるソフトもあります。

デザインと宛名が完成したら、いよいよ最後の印刷です。
- プリンターの準備をする
プリンターの電源を入れ、パソコンと接続されていることを確認します。
インク残量に問題がないか、用紙は正しい向きでトレイにセットしたかどうか確認しましょう。 - テスト印刷をする
いきなり本番のはがきに印刷せず、まずは普通の紙(A4用紙など)で「試し刷り」をすることを強くおすすめします。
年賀状ソフトの印刷画面で「試し刷り」「テスト印刷」のボタンを探し、1枚だけ印刷してみましょう。
文字がはみ出していないか、写真の色味は問題ないかなどを確認します。 - 本番の印刷を開始する
テスト印刷で問題がなければ、印刷画面で「すべてを印刷」または印刷したい宛名を選択し「印刷開始」ボタンをクリックします。
「特定の操作方法がどうしてもわからない」「エラーが出て印刷できない」場合は
So-net 安心サポートへの相談をおすすめします。
\ So-net 安心サポートに相談! /
So-net 安心サポート(電話+リモートサポート)の情報が見つかり、お困りごとを解決するための一助となれば幸いです。